
岡由雨子建築ディザイン株式会社
代表取締役
岡 由雨子 氏

MITO architecture + design
代表・建築家
三戸 景 氏
長い時間にわたって使われ、愛される建物を
横浜市中区の馬車道。江戸末期に横浜港の開港にともない、1868年に関内と横浜港を結ぶ道の一つとして開通したこの通りには、いまも煉瓦の舗装やガス灯による街路灯など往時の雰囲気が色濃く残り、数々の歴史的建築物が建ち並んでいる。その一つ、「馬車道大津ビル」は横浜市認定の歴史的建造物。ニューヨークのアールデコ建築を彷彿させる築80年余のこの建物の地下一階に、岡由雨子建築ディザインのオフィスが置かれている。
「実はとても個人的なことなのですが、私はこの建物に恋をしたんですよ」。そういって岡氏は笑う。「古いものに魅かれるのでしょうね。この建物もかなり古いですが、オーナーがとても奇麗に保ってくださっていて。長い時を超えて多くの人が愛情を注ぎ、守ってきた──そんな風に感じさせてくれる空間だったのです」。そして、それはそのまま、岡氏が創りたいと考えている建築のあり方も示している。
「私も多くの皆さんが長い時間にわたって使ってくださる建物、多くの方に愛されるような建物づくりに携わっていきたいのです。現在はいろいろな御縁もあって集合住宅を数多く手がけていますが、公共性のある建築にも目を向けています」。そして、だからこそ日本の建築業界でBIMの普及が始まると、岡氏は躊躇なくその導入に踏み切った。岡氏自身は学生時代から手描きと合わせて2D CADも学んだ世代。建築家として当初からCADを使ってきたが、多くの先輩たちのCADに対するさまざまな取組みスタンスを見てきたことが、BIM導入の決断を後押ししたという。
「自分が生きている時代の新しい技術はみずから率先してこれを学び、取り入れていこうと思ったのです」。こうして、岡氏は2017年からBIMの導入検討を開始した。
「BIMツールに関する情報を仲間たちと交換しながら最終的に選んだのがARCHICADでした。普段使っている画像/イラスト編集ソフトにUIが近く、初めて触れるBIMとして動作がシンプルで、かつ初動時に使いやすい図面テンプレートが整備されていることが決め手となりました」
「やるしかない!」状況を作り出すために
事務所の「仕事の仕方」をテンプレート化!
一人一人のスキルを事務所としてのスキルへ確立し拡大していくことを目指す
「とにかく始めたばかりの個人事務所だったので、何でも自分でやらなければなりません。ところが、私はもともとパース作りが得意ではなかったので、コストと時間をかけて外注するしかありませんでした」。そうなると、まず図面を作って他ソフトで3D化し、さらにパースを作り……と作業を分割して進める必要があるが、この進め方そのものが、岡氏には非効率で改革すべきものと思えたという。
「だからできるだけ早くBIMを導入し、これらの作業を3次元でトータルに進めて、図面やパースも一気に生成するなど効率的に進められるようにしたかったのです」。岡氏にとってこのことは、単なる効率化というだけの問題ではなかった。その背景には、自らの事務所経営に関わる岡氏ならではの方法論があった。
「個人の仕事もそうですが、事務所としてやっていく以上は、“事務所としての仕事の仕方”をきちんと練りあげて、これをテンプレート化して蓄積していくべきと考えていました。そうすることで、個人が持っているスキルを事務所全体のスキルへと拡大していけるからです」。そして、そのためにカギとなるのがBIMだった。BIMによる設計手法を確立しテンプレート化して、これを「事務所のスキル」へ育てていこうというのである。
こうしてARCHICADの導入を決めた岡氏だったが、事はなかなか思い通りには進まない。実際にARCHICADが届くと、仕事に追われて触ることもできないまま一カ月も放置することになってしまったのである。そんな状況に風穴を開けたのが、依頼を受けたばかりの新プロジェクトだった。それは北海道函館市で計画されていた新たな集合住宅の建築計画で、その受注を機に岡氏は思いきった決断を行う。まだ使いこなせていなかったARCHICADをメインツールに、この新しいプロジェクトをBIM設計で行うと決めたのである。
「もちろん、BIMでやることを施主から要望されたわけではありません。とにかく自分を追いつめて“やるしかない”状態にしなければ、と思ったんですね。空いた時間にやろうとか、片手間でやろうとしても結局は身に付かないわけで。新規プロジェクトにあえて慣れないARCHICADを投入し、背水の陣で取り組んだのです」。
BIM先進国からやってきた助っ人
岡氏が「函館プロジェクト」と呼ぶその新規案件は、函館市の中心地からすぐの住宅地内の賃貸マンションの建築計画だった。近隣の区画にはすでに同ブランドのマンションが3棟ほど完成しており、岡氏が任されたのは、このデザイナーズマンションのシリーズとして4棟目となる最新物件だった。
「函館市は総合病院が多い土地なので、そこへ赴任される医師の方やその家族の住居として企画されたマンションで、地上4階建てのRC建築に3LDKのみ30戸を用意。さらにスポーツジムも備えた、延床面積約5,000㎡の建物を構想しました。そして、お施主様からは“経済設計”を求められていたので、なるべくコストのかからない方法を、とさまざまな形で模索していきました」。──ところが、図面制作に着手後、プロジェクトの進行は早くも滞りはじめる。
「とにかく背水の陣で取組んだのですが、やはりARCHICADの操作で躓いてしまいました。3Dモデルを立ち上げるあたりまでは何とかクリアできたのですが、それを図面化しようとすると、どうしても思うようにできなくて」。長年、2D CADで設計を行ってきた岡氏の中では「2D図面はこうあるべき」というルールができ上がっており、前述のBIMによる図面作成の方向性も当初からかなり細かい所まで見えていたという。だが、そのことが逆に岡氏の足かせとなった。その方向性に沿って「事務所スタンドード」の図面を作ろうとすると、さまざまな要素が絡み合い作業を立ち往生させてしまうのである。
「基本設計も進んでいたのに、どうやったら良いか分らなくなってしまって……正直すごく焦りましたね。そして、切羽詰まってグラフィソフトの方に“BIMで実施図まで作れる人を紹介してください”とお願いしました。そして、紹介していただいたのが、ニューヨークで建築家として活躍し、BIMにも詳しい三戸景さんだったのです」。
フランス生まれの岡氏とニューヨークから帰国したばかりの三戸氏という二人の稀な出会いが、両氏にとって大きなブレイクスルーのきっかけとなる。──この日も岡氏のオフィスで作業しておられた三戸氏に、まずそのユニークなキャリアから紹介してもらった。
「私の場合、まず日米両国で建築学の修士号を取得した後、そのままニューヨークで就職。20数年にわたってSOMやPolshek Architects(現 Ennead Architects)など多くの建築設計事務所を渡り歩いてきました。あちらでは、そういうパターンが多いんですよ。そして2010年に独立し多くのプロジェクトを手がけた後、2017年に帰国しました。岡さんに声をかけられたのは、その帰国後すぐでしたが、そのまま函館プロジェクトの仕事をお手伝いすることになったのです」。BIM先進国であるアメリカの建築業界で長年活動してきた三戸氏は、BIM設計に関しても、本場で学んだ豊富な知識と実務経験に基づいた多彩なノウハウを蓄積している。むろんBIMツールについても一家言を持っている。
「実際、向こうではBIMを普通に使っていました。最後の職場でも他社製BIMソフトを使っていたし、他にもいろいろ3Dツールを使う機会がありましたね。ただ、有名なソフトでもなかなか使いやすいと思える製品がなくて、独立時にあらためて自分に合ったBIMソフトを選び直すことにしたのです」。そこで三戸氏はあらためてリサーチを行い、最終的に選んだのがARCHICADだった。「一番の選定ポイントは直感的な操作性ですね。やはり感覚的にデザインしながら建築設計していけるところがすごくピッタリ来るし、使いやすいですよね」。こうして導入したARCHICADを駆使し、ニューヨークでさまざまな建築やインテリアのプロジェクトに携わった三戸氏は、帰国後も通常の設計業務や他プロジェクト支援を行っているほか、ARCHICADによるBIM導入サポートや専門学校でBIM設計の講師も務めているという。──ともあれ、こうして始まった両氏のBIM設計コラボは、やがて誰も想像しなかったユニークな発見へと繋がっていった。
日米の図面制作手法の違い
図面全体の骨格と精密なリンクを重視し合理的で使いやすいデータベースを作りあげる、アメリカンスタイルの図面作成法の驚き
「最初はARCHICADの基本の基本から……それこそインターフェイスの解説から2日くらいかけて教わり、それから作業に入りました。すでに契約も済んでスタートしていたプロジェクトでしたから、納品すべき図面の種類や期日も定まっていました。そこで“これとこれとこの図面を、この日までに仕上げなければならない。どうすれば?”と、率直に相談を持ちかけたのです」(岡氏)。
ところが、長年日本を離れてアメリカの設計業務に携わってきた三戸氏は、帰国当初に日本で触れた図面から、渡米前に知っていたそれと全く異なる印象を受けていたのだという。そして、その後も三戸氏は、岡氏に声をかけられた時まで、日米の図面制作手法の相違に疑問を持ち続けていたのである。では、三戸氏は、日米の図面の何処にそれほど大きな違いがあると感じたのだろうか?
「アメリカでは、図面もきわめて合理的に作られています。しかも、その統一されたスタイルが業界で共有され、スタンダード化されているのですね。だから誰が見ても理解できるし、どの事務所へ移っても即戦力として活躍できるのです」。ところが日本ではそれは難しい、と三戸氏は言う。図面自体の表現が不十分で一貫してない上、事務所ごとに整理の仕方が異なり、各社の自己流になっていることさえ少なくないのだという。
「図面であるにも関わらず、情報を読み取ることがとても難しくなっているように思えました。それは岡さんの図面が、ということではなく、他所のものも含めて日本の図面そのものが持つ特性だと思えたわけです」(三戸氏)。一方、当初、三戸氏の言う内容がなかなか飲み込めなかった岡氏も、あらためて自身の描く図面を見直していくうち、「たしかにこれでは分かり難くい」と感じる箇所が次々と見えてきたという。
「三戸さんから“アメリカではこんな風に描いている”と話してもらい、私も日本流の作図方法をいろいろ伝えて、二人で日米両国の図面作りスタイルを比べていったのです。そして、双方の図面に長所と弱点があり、お互い学ぶべき所がたくさんあることに気づきました」。ならばアメリカ式の図面の良い所も活かし、日本のBIMに適した「本当に分かりやすい図面」を作るべきだ──そう二人は考えた。そして、この試みで大きな威力を発揮したのがARCHICADだった。
日米双方の良い部分を調整&融合
「たとえばアメリカの図面では、基本的に文字情報よりも記号や符号、凡例等を多用します。これらを用いて、図面内のさまざまな要素を全て明確にリンクしているのです。一方、 日本の図面にはそうしたリンクの意識がほとんどありません。そのため図面同士の関連がはっきりせず、要素の説明も舌足らずになりがちで、慣れない人間には内容が伝わり難いのです」。そう語る三戸氏によれば、米国式の図面ではその全てにシート番号と図面番号が付けられており、これらの番号・符号によって各要素が分かりやすく結ばれているのだという。 しかも、そのリンクはARCHICADが備えているマーカーツールの機能を使うことで容易に作成できるのである。当然といえば当然だろう、ARCHICADというツール自体が、海外の設計手法を参考に開発されたものなのだから。
「たとえば断面図だったら、平面図上の断面図符号にシート番号と図面番号が付き、対応する断面図の側にもシート番号と図面番号が付いています。そこで平面図のこの箇所の断面を確認したいと思ったら、その断面図符号に書かれている図面番号を見てその図面を確認することができる。設計全体の骨格とそれぞれのリンクがとても重視されているわけです。そしてARCHICADを使うと、断面図符号をクリックすることにより、リンク経由で即座に確認したい断面図へとジャンプ出来ます」(三戸氏)
「一方、日本の場合は、ご存知の通り平・立・断に矩計と、まず図面の種類が求められます。仕上表に建具表といった図面リストみたいなものはありますが、“それらをどう整理するか”についてはスタンダードなやり方が存在しません。だから、図面を見ていてある箇所の詳細を知りたいと思っても、どの書類に書いてあるのか、すぐに分からないわけです」(岡氏)。さらに言えば、日本式の図面では、その様式のため詳細な情報が省略されてしまうことも多い。たとえば下地に関する情報など、仕上表を見ても網羅しきれてないことがほとんどだという。「そこからどうやって数量を拾い出しているのかといえば、多くの場合、施工会社が経験に基づいて想像しているわけで……。 結果として、現場で確認せざるを得ない箇所が多くなってしまうわけです。情報を正しく漏れなく伝えるべき設計図としては、やはり不親切というしかないでしょう」(岡氏)
このように比べていくと、米国式の図面は設計全体の骨格を示し、伝えるシステムがきわめて合理的な作りとなっていることが分る。設計意図と施工に必要な細かな情報を網羅し、しかもそれらを「いかに明確に分かりやすく伝えるか」整理し、それを合理的なシステムに落し込んでいるのだ。「誰が見ても……たとえ言葉が分らない方でもこの図面なら読むことができる。そんな仕組みになっているんです」(三戸氏)
もちろん函館プロジェクトでは日本式の図面が求められている。いくら合理的なものであっても、米国式の図面をそのまま作って納品するわけには行かないのは当然だ。岡氏と三戸氏は限りない議論を重ねながら米国式図面の良い所を抽出。それを日本式の図面表現へと落し込んで、さらにそのためのARCHICADの操作法を試行しながら、二人三脚で1つ1つ図面へと仕上げていった。それはまさに、プロジェクト前から岡氏が目指していた目標──事務所のスタンダードとしてテンプレート化するに相応しい、図面スタイルを築いていくための挑戦にほかならなかった。
BIMを活かした図面整理の方法論
函館プロジェクトで確立した図面スタイルを、さまざまなプロジェクトに応用しながら、一つ一つノウハウを蓄積して事務所の財産に
「図面を描くより、“どう作るか”二人で試行錯誤することに大変な時間がかかってしまいましたが、どうにかこうにか……三戸さんには苦労をかけましたが……計画通り図面は仕上り、無事着工して現在は基礎工事が進んでいます」。そういって岡氏は苦笑いする。「今回は最初のBIM設計チャレンジであり、図面作りの方法論から考える必要があったから一番大変だったのではないでしょうか。次のプロジェクトはもう少し余裕が出てくるんじゃないかな」と両氏とも笑顔になる。だがもちろん、事務所スタンダードの確立を目指す挑戦はまだ道半ばである。岡氏は語る。
「特に図面整理のためにARCHICADをどう使うか……マーカーをどのスケールの時何処へ置くか?壁はどう整理するか?建物全体に対してどう切っていくか等々、米国式を活かした図面整理の方法論はある程度基盤ができました。あとはこれをいろいろなプロジェクトに応用しながらノウハウを蓄積していけば、一つ一つが事務所の財産になっていくでしょう。実は次のプロジェクトで、すでにこれを応用しているんですよ。……やはりまだまだ試行錯誤の連続ですが(笑)」
Archicadの詳細情報はカタログをご覧ください
ー カタログと一緒にBIMユーザーの成功事例もダウンロードできます ー
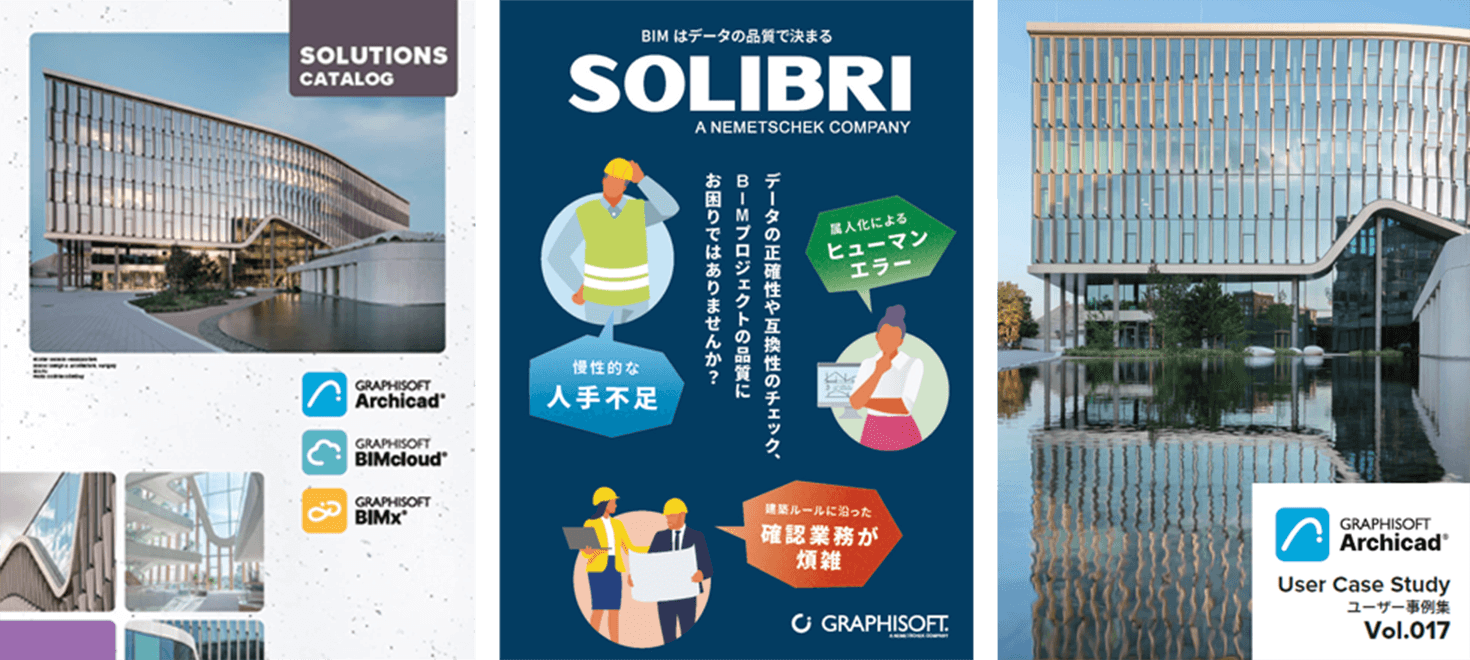
- Archicad ユーザーの設計事例を紹介
- 設計時の裏話や、BIMの活用方法など掲載
- その年ごとにまとめられた事例をひとまとめに
- BIM導入前から導入後の情報満載









